RPAとは?基本的な仕組みや導入メリットを徹底解説!
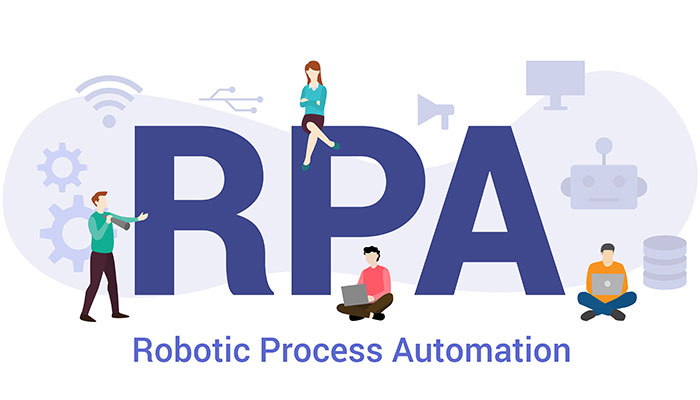
「RPAって何?」「社内の業務を自動化する方法が知りたい」
そんな方に向けて、この記事ではRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の基本から、仕組み・できること・導入の流れまでわかりやすく解説します。
RPAは、パソコン上の定型業務をソフトウェアのロボットが自動化することで、作業時間の短縮や人手不足の解消、業務品質の安定化といった多くのメリットをもたらします。
RPAの導入を検討している企業のご担当者やRPAについてゼロから学びたいという方にとって必見の内容です。
1.RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは?簡単に解説
RPAとは、ロボットのカタチをした機械?と思われている方も多いかもしれません。ここでは「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)」とは何か、基礎的な知識にわかりやすく解説します。
■事務作業などのPC操作を自動化するソフトウェア
RPAとは、パソコン上で行う業務を自動化するソフトウェアを意味します。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、「ロボットによるプロセスの自動化」を意味します。ロボットと言っても形のある機械のロボットではなく、パソコン上にインストールされたソフトウェアのことです。
■Excel入力やメール送信などの単純作業を自動化
RPAでは、これまで人間が行っていた定型業務を自動化するため、業務効率の向上やミスがなくなるなどのメリットがあります。
エクセルの入力作業やデータを他のシートに入力しなおす作業のような定期的に必要で、なおかつ手間のかかる作業を自動化することにより、その業務の担当者は本来注力すべき業務に集中できるようになり、全体の生産性向上が期待できます。
現在、RPAは大企業だけでなく、中小企業でも業務改善のツールとして導入が進んでいます。
2.RPAの仕組みとは?自動化できる業務内容とその特徴
RPAは、あらかじめ設定されたルールや手順(シナリオ)に基づいて、定型業務を自動で実行します。これにより、複数のソフトを横断するような業務や、大量のデータ処理にも対応できます。
ここでは具体的にどのような業務がRPAによって自動化できるかを解説します。
■RPAの基本的な仕組み
RPAが得意とするのは、マニュアル化された作業や繰り返し行う必要のある定型業務です。
一方で、人の判断が必要な仕事や、臨機応変な対応が求められる業務には向いていません。
<対応できる業務(どんな業務に向いているのか)>
| RPAに向いている業務 | 業務内容例 |
| 入力業務 | ・エクセルから専用システムへの入力 ・CSVデータをシステムに転記する ・顧客管理システムへの入力 |
| 集計業務 | ・Web上のデータを収集 ・集計 |
| データ加工 | ・エクセルやCSVのデータからの集計やグラフ作成 |
| メール送信 | ・HPからの問合せへの自動返信 ・お客様ごとに異なるメールの作成 ・送信 |
| ファイル保存 | ・受信メールの添付ファイルを社内のフォルダに保存 |
3.RPA導入のメリット
RPAの導入にはさまざまなメリットがあります。ここでは代表的なメリットをご紹介します。
■業務効率化
最も大きなメリットは、ルーティン作業を自動化することにより、作業時間が短縮され、業務効率化を図れることです。
また、RPAによって24時間いつでもデータの処理となるため、生産性が向上します。
従業員はこれまでルーティンワークに取られていた時間を有効に活用し、より生産性や付加価値の高い業務に注力できるようになります。
従業員が単純作業から解放され、より企業のコア業務に関われるようになれば、仕事のやりがいや満足度の向上も期待できます。
■コスト削減大量のデータ処理も迅速
RPAの活用により、コストを削減できるのもメリットです。これまで定型業務に追われていた繁忙期も、より少ない人数で大量の作業をこなすことが可能になります。人材の採用コストや教育コストも削減できるでしょう。
■ミスを減らし、業務品質の安定化
人間が手作業で行っていた場合、ミスが起きてしまうことは避けられません。
RPAの導入により、大量のデータでもスピーディかつ正確に処理できるため、業務品質が安定します。
またミスを防ぐためのチェック作業や修正の作業などのコストや時間も削減できます。
作業効率が高まり、仕事のスピードが上がることで顧客満足度を向上させる効果も期待できます。
4. RPAは人の仕事を奪うのか
RPAにより、人の仕事が奪われるのではないかという不安の声もあります。
しかしRPAが完全に人の仕事を奪うということはありません。
RPAが自動化できるのは、あくまでも単純作業や定型的なルーティンワークに限られるからです。
■RPAができる作業と人が行うべき業務
RPAは主に次のような役割を担っています。
・人がより価値ある仕事に集中できる環境をつくる
・担当者がより重要な業務に集中できるようになる
RPAの導入により、従業員はより付加価値の高い業務にシフトしていくことができるのです。
■定型業務の中でも残る仕事
定型業務がRPAにより削減されたとしても、最終チェックの業務は人間による確認が必要なため、RPAにすべてを任せきることはできません。そのため、定型業務であってもRPAにより完全に仕事が奪われるというわけではありません。
むしろRPAは近年の人材不足の課題を解決する手段としても注目されているのです。
5. RPAとAI、どちらを導入するべきか
業務効率化のためにRPAとAIどちらを導入するべきかという議論もあります。
結論から言うと、RPAとAIの組み合わせでより効果的な業務改善が可能です。
ここでは、RPAとAIの役割や組み合わせによる活用法についてご紹介します。
■RPAとAIの役割の違い
AI(アーティフィシャルインテリジェンス)とは人間の脳のような知能を再現した人工知能です。
AIの特徴は、膨大なデータから自ら学習して問題解決を行うことができることです。
RPAとAIの基本的な役割の違いは以下のようになります。
RPA:業務を自動化するシステムそのもので、決められたルールに従って作業を行う
AI:システム内に組み込まれ、データに基づいた判断を行う
つまり、ルールに基づいて作業を行うのがRPA、AIは単体で業務の自動化などを実現できるわけではなく、システムに組み込まれることで機能するのです。
■RPAとAIの組み合わせでより高度な自動化を実現
ルールに基づいた作業の自動化を行うRPAと、自ら学習して課題に対処するAIを組み合わせることで、より高度な業務プロセスの自動化を実現することが可能になります。
RPAには、Class1からClass3まで、3つの自動化レベルがあります。
●Class1:定型業務の自動化
●Class2:一部非定形業務の自動化
●Class3:高度な自律化
現在、主流となっているのはClass1の定型業務の自動化です。
しかしClass2以降の非定形業務の自動化や、業務改善や意思決定を含む自動化についてはRPAだけでなくAIとの組み合わせにより可能となります。
今後、AIツールがさらに普及すれば、RPAとAIの組み合わせにより複雑な業務も自動化されていることが予想されます。
6.RPA導入までの流れと成功のポイント
それではRPA導入の流れについてのポイントをご紹介します。
RPAはプログラミングの知識がない人でも、比較的簡単にパソコン1台から導入できる手軽さも特徴の一つです。
しかし、いくつか注意点もあります。
■導入する業務をリストアップ
RPAの導入にあたって、どの業務にその部分にRPAを導入して自動化するべきかを検討し、その範囲や優先順位を決めておくことが需要です。
導入範囲によっては、逆に作業量が増えてしまうこともあるからです。
そのため部分的な業務からはじめて徐々に拡張していくのがおすすめです。
■ツールの選定
対象業務に適したツールの選定は重要です。
RPAのツールは数多くの企業から販売されています。会計業務や採用業務に特化したものなど、製品ごとに特徴が異なるため、対象業務に適したツールを選ぶ必要があります。
また導入後のサポート体制が充実しているかどうか、費用対効果、使いやすさなどさまざまな面から検討し、ベストなツールを選定することが効果的な導入につながります。
■トライアルと検証、修正
RPAツールを導入したら、シナリオ(作業手順)を作成します。シナリオはRPAツールの機能を使って作成することができます。
シナリオができたら、まずテスト導入と検証を行う必要があります。想定通りにRPAツールが動くかどうかを確認し、細かく修正を行って誤作動や見落としを防ぐことも必要です。
RPAの導入には、スモールスタートで少しずつ始め、徐々に拡大していくのが最も効率的で高い効果につながります。
7.まとめ
定型業務の効率化のためにRPAの導入を進める企業が増えています。
RPAの活用により、従業員は定型業務のルーティン作業から解放され、コア業務に注力できるようになることや、コストを削減できる点は非常に大きなメリットです。
RPAの導入には、事前に自動化すべき業務の洗い出しやツールの選定、テスト検証などさまざまなプロセスがあります。
自社にあった効果的なRPA導入は、コウシンの「ゼロからはじめるRPA」のサポートをぜひご活用ください。
\10倍楽するRPA仕事術/
ホワイトペーパープレゼント
RPAに関するご相談はお気軽にどうぞ
まずは無料相談で今後のアクションを明確にすることができます。生産性向上に向けた第一歩を踏み出しましょう!






